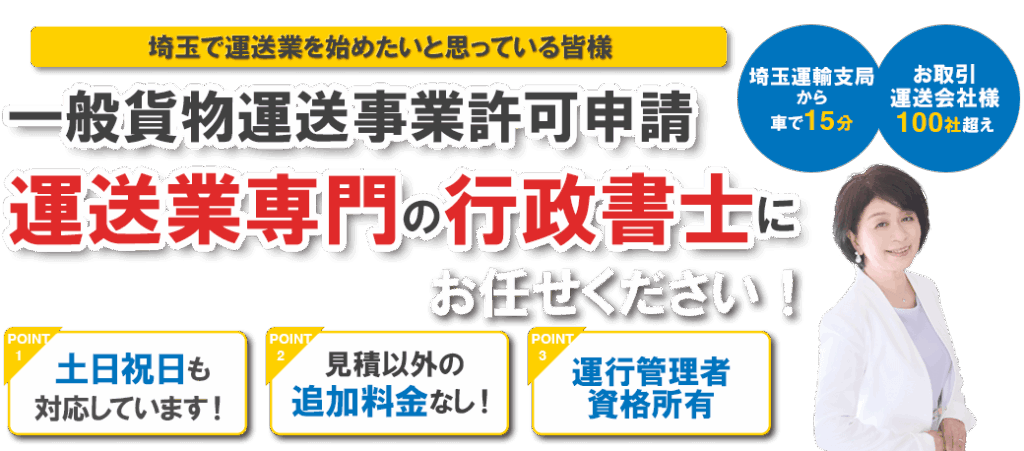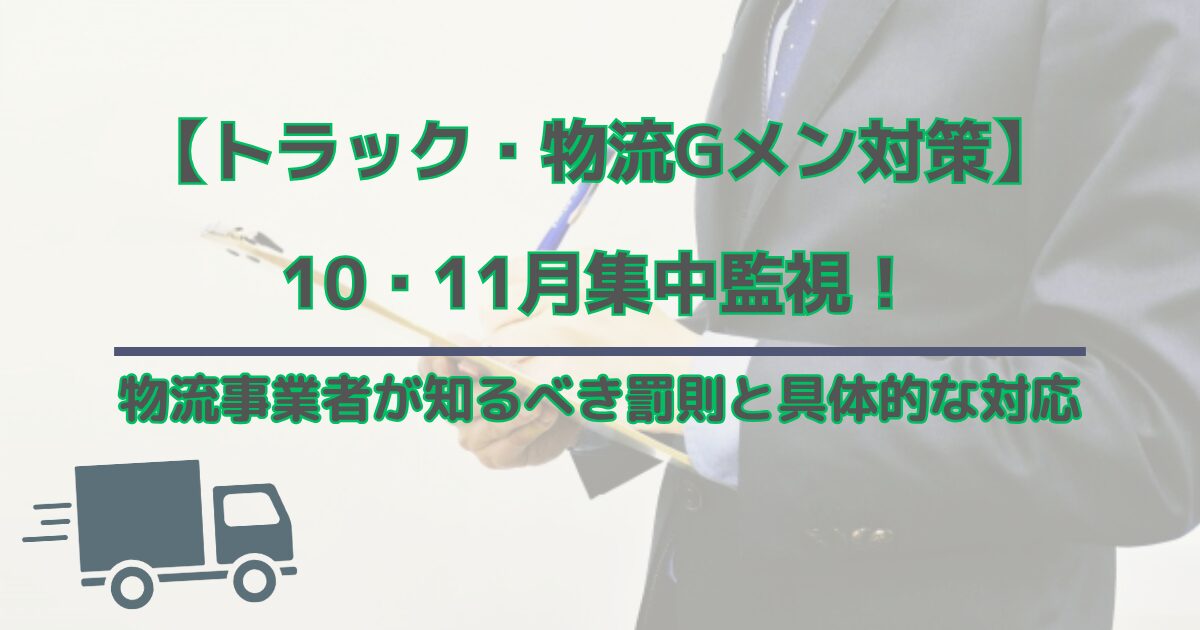物流業界に携わる皆様、日々の業務お疲れ様です。
近年、私たちは「物流2024年問題」に代表されるような、ドライバー不足や労働環境改善など、多くの課題に直面しています。
こうした課題を受けて、国土交通省は物流の適正化を一層推進するため、新たな取り組みを強化しています。その中心となるのが「トラック・物流Gメン」による監視体制の強化です。
特に、10月・11月は「集中監視月間」として、その監視体制は普段以上に厳しくなります。
本記事では、国土交通省が強化しているトラックGメン(トラック・物流Gメン)の監視内容と、10〜11月の集中監視月間に向けて物流事業者が取るべき具体的な対策を解説します。
なぜトラックGメンが重要視されるのか?物流を取り巻く現状
まず、トラックGメンの重要性を理解するために、現在の物流業界が抱える課題について改めて確認しておきましょう。
深刻化するドライバー不足と「物流2024年問題」
ご存知の通り、物流業界は慢性的なドライバー不足に悩まされています。高齢化の進展に加え、若年層の流入が少ないことが大きな要因です。
さらに、2024年4月1日からは、働き方改革関連法によりトラックドライバーの時間外労働に上限規制が適用されます。これにより、ドライバー1人あたりの労働時間が短縮されるため、これまでと同じ量の輸送を行うにはより多くのドライバーが必要となります。これが「物流2024年問題」として、業界全体に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。
【ミニ解説】物流2024年問題とは?
2024年4月1日から適用されるトラックドライバーの時間外労働時間の上限規制(年間960時間)によって発生する、物流業界が直面する様々な課題の総称です。具体的には、ドライバー不足の深刻化、輸送能力の低下、運賃上昇、企業収益への影響などが懸念されています。業界全体で、労働環境の改善や生産性向上への対応が急務となっています。
荷待ち・荷役時間の長時間化
ドライバー不足に加え、深刻な問題となっているのが「荷待ち・荷役時間」の長時間化です。
トラックドライバーが荷主の倉庫や配送センターで荷物の積み込みや積み下ろしを行う際、長時間待機させられたり、荷役作業に時間がかかったりすることが少なくありません。これはドライバーの労働時間を圧迫し、結果として賃金低下や休息時間の減少につながります。
この長時間労働は、安全運転の阻害要因にもなりかねず、またドライバーの離職を加速させる一因ともなっています。
下請け構造による運賃の適正化の課題
物流業界の多重下請け構造も、運賃の適正化を阻む要因となっています。
元請けから下請け、孫請けへと仕事が流れる中で、運賃が適正に配分されず、最終的に現場で働くドライバーの収入が低い水準に留まってしまうケースが見受けられます。これは、ドライバーのモチベーション低下や、ひいては業界全体の魅力低下につながりかねません。
このような状況を改善し、持続可能な物流システムを構築するためには、業界全体のコンプライアンス意識を高め、適正な取引慣行を確立することが不可欠です。
そのための具体的な手段の一つとして、「トラック・物流Gメン」が設置されました。
トラックGメンとは?その役割と目的
トラックGメンとは、国土交通省が設置した「貨物自動車運送事業法に基づく適正化事業指導員」の通称です。
彼らの主な役割は、トラック運送事業における荷主や元請け事業者に対する指導・要請を通じて、荷待ち・荷役時間の削減や適正な運賃・料金の収受を促進することにあります。
トラックGメン設置の背景と目的
トラックGメンは、2023年7月21日に本格的な運用が開始されました。
その背景には、前述したような物流業界が抱える喫緊の課題への対応があります。特に、「物流2024年問題」を見据え、ドライバーの労働時間短縮と労働条件改善を促進することが最大の目的です。
具体的には、以下の3つの目標を掲げています。
- 荷待ち・荷役時間の削減:荷主や元請け事業者に対し、荷待ち・荷役時間を削減するための改善計画の策定や実施を要請します。
- 適正な運賃・料金の収受:下請け事業者への不当な運賃減額や、燃料高騰分を運賃に転嫁しないなどの不公正な取引を是正します。
- 物流の効率化と生産性向上:上記2点を通じて、物流全体の効率化と生産性向上を図り、持続可能な物流システムの構築を目指します。
トラックGメンの具体的な活動内容
トラックGメンは、全国の地方運輸局に配置されており、以下のような活動を行います。
- 情報収集:ドライバーからの情報提供、運送事業者からの相談、巡回指導等を通じて、荷主や元請け事業者による法令違反行為や不適正な取引に関する情報を収集します。
- 荷主・元請け事業者への指導・要請:収集した情報に基づき、荷主や元請け事業者に対して、荷待ち・荷役時間の削減、適正な運賃・料金の支払いを求める指導や要請を行います。
- 立ち入り検査:必要に応じて、荷主や元請け事業者に対して立ち入り検査を実施し、帳簿や書類の確認を行います。
- 是正勧告・命令:指導・要請にもかかわらず改善が見られない場合や、悪質な法令違反が確認された場合には、是正勧告や是正命令を行います。
- 公表:特に悪質な違反行為については、企業名を公表するなどの措置をとることがあります。
トラックGメンは、従来の指導監督とは異なり、荷主や元請け事業者に対して直接指導・要請を行う権限を持っている点が大きな特徴です。これにより、物流のサプライチェーン全体にわたる適正化が期待されています。
10月・11月は集中監視月間!体制強化の背景と注意点
国土交通省は、トラックGメンによる監視体制を特に強化する期間として、10月と11月を「集中監視月間」と定めています。
これは、年末に向けて物流量が増加する時期であり、それに伴うドライバーの長時間労働や不適正な取引が増加する傾向にあるためです。
集中監視月間の背景と目的
年末商戦や歳暮シーズンなど、10月から11月にかけては小売店やECサイトでの需要が高まり、物流の動きが活発になります。
この時期は、人手不足の中、通常の業務に加え、物量の増加に対応するため、ドライバーへの負担が大きくなりがちです。
結果として、荷待ち・荷役時間の長時間化や、無理な運行指示、不当な運賃交渉といった不適正な取引が発生しやすくなります。
集中監視月間は、こうした状況を未然に防ぎ、ドライバーの労働環境を守るとともに、物流の安全と安定を確保することを目的としています。
強化される監視体制と重点項目
集中監視月間中は、トラックGメンによる情報収集や指導・要請が普段以上に活発に行われます。
特に以下の点に重点を置いて監視されることが予想されます。
- 荷待ち・荷役時間の長時間化の有無:トラックドライバーが荷主の施設で長時間待機させられているケースや、荷役作業に不当に時間がかかっているケース。
- 不適正な運賃・料金の取引:燃料価格の高騰を運賃に転嫁しない、下請け事業者への不当な運賃減額、書面契約がないままの取引など。
- 再委託の制限違反:運送事業者が荷主から依頼された運送業務を、さらに別の運送事業者に丸投げする「再委託」には制限があります。特に、許可なく再委託を行う行為は厳しく取り締まられます。
- 運行管理の不徹底:過労運転の防止、適切な休憩時間の確保、健康状態の確認など、運行管理が適切に行われているか。
集中監視月間における情報提供の奨励
国土交通省は、集中監視月間中、不適正な取引に関する情報提供を積極的に奨励しています。
ドライバーや運送事業者からの匿名での情報提供も受け付けており、これらの情報がトラック・物流Gメンの指導・要請活動に活用されます。
「声を上げにくい」と感じる事業者やドライバーの声が、改善のきっかけとなることが期待されています。
違反行為に対する罰則と事業者が負うリスク
トラックGメンによる指導・要請にもかかわらず、改善が見られない場合や、悪質な法令違反が確認された場合には、厳しい罰則が適用される可能性があります。
これらの罰則は、荷主、元請け事業者、そして運送事業者のすべてに適用される可能性があるため、自社の事業が関連法規に準拠しているかを改めて確認することが重要です。
荷主・元請け事業者に対する罰則
荷主や元請け事業者に対しては、主に以下の措置がとられる可能性があります。
- 是正勧告・是正命令:荷待ち・荷役時間の長時間化や不当な運賃交渉が改善されない場合、国土交通省は是正勧告を行い、それでも改善が見られない場合には是正命令を出します。
- 企業名の公表:是正命令に従わない場合や、特に悪質な違反行為が確認された場合、企業名が公表される可能性があります。企業名の公表は、社会的な信用失墜につながり、取引先からの信頼喪失や顧客離れを引き起こす深刻なリスクとなります。
- 勧告制度の適用:荷主勧告制度に基づき、荷主に対して改善を要請し、従わない場合は勧告を行います。この勧告に正当な理由なく従わない場合、勧告の事実を公表される可能性があります。
- 運送事業者に対する許可取り消し等の行政処分(間接的影響):荷主・元請け事業者の不適正な行為が原因で、運送事業者が過労運転や過積載などの法令違反をせざるを得ない状況に追い込まれた場合、運送事業者が行政処分を受ける可能性があります。この場合、荷主・元請け事業者も責任を問われる可能性があります。
【ミニ解説】荷主勧告制度とは?
貨物自動車運送事業法に基づき、荷主の行為が原因で運送事業者が過積載運行や過労運転などを引き起こすおそれがある場合に、国土交通大臣が荷主に対して、原因となる行為の停止や改善を要請・勧告できる制度です。勧告に従わない場合はその事実が公表されることがあります。これは、荷主側にも適正な取引を求めるための重要な制度です。
運送事業者に対する罰則
運送事業者自身が法令違反を犯した場合、トラックGメンの指導対象となるだけでなく、国土交通省による行政処分の対象となります。
具体的な罰則は以下の通りです。
- 車両停止命令:過積載、過労運転、点検整備不良など、安全運行に支障がある場合に車両の使用が停止されます。
- 事業停止命令:運行管理体制の不備、悪質な法令違反、再三の指導にもかかわらず改善が見られない場合に、事業の一部または全部が停止されます。
- 事業許可の取り消し:極めて悪質な違反行為、是正命令への不履行、再度の事業停止命令など、重大な法令違反が確認された場合に、事業許可が取り消されます。これは、運送事業を継続できなくなる最も重い罰則です。
- 罰金:無許可営業、虚偽の届出、運行記録の改ざんなど、貨物自動車運送事業法に違反した場合、罰金が科せられることがあります。
- 行政処分点数の付与:違反行為に応じて行政処分点数が付与され、累積点数に応じて車両停止や事業停止などの行政処分が課されます。
これらの罰則は、事業の継続を困難にするだけでなく、企業の社会的信用を失墜させ、取引関係にも悪影響を及ぼします。
そのため、すべての関係事業者が法令遵守の意識を高め、適切な事業運営を行うことが極めて重要です。
トラックGメン 集中監視月間に向けた事業者・荷主がとるべき具体的な対策
集中監視月間を滞りなく乗り切り、将来にわたって健全な物流事業を継続していくためには、事前の準備と継続的な改善努力が不可欠です。
ここでは、運送事業者と荷主・元請け事業者の双方に求められる具体的な対策について解説します。
運送事業者がとるべき対策
運送事業者様は、トラックGメンの指導対象となる可能性のあるリスクを減らすために、以下の対策を徹底してください。
- 運行管理の徹底と記録の適正化
- デジタコ・ドラレコの活用:デジタルタコグラフやドライブレコーダーを導入し、運行時間、休憩時間、速度などを正確に記録・管理しましょう。これにより、過労運転の防止や事故時の状況把握に役立ちます。
- 運行日報の正確な記録:荷待ち時間、荷役時間、休憩時間など、ドライバーの拘束時間を正確に記録し、長時間労働を未然に防ぐ体制を構築しましょう。
- 健康状態のチェック:ドライバーの点呼時に、体調や睡眠状況を確認し、無理な運行をさせないように徹底しましょう。
- 荷主・元請け事業者との交渉記録の保持
- 書面による契約の徹底:運送契約は必ず書面(契約書や発注書など)で交わし、運賃、料金、付帯業務の内容、荷待ち・荷役時間の取り扱いなどを明確にしましょう。
- 不当な要求があった場合の記録:荷主や元請け事業者から、不当な運賃減額、長時間待機、無理な運行指示などの要求があった場合は、その日時、内容、担当者などを詳細に記録しておきましょう。必要に応じて、トラックGメンへの情報提供の際に役立ちます。
- 燃料サーチャージの協議:燃料価格変動に応じた運賃調整(燃料サーチャージ)について、事前に荷主・元請け事業者と協議し、取り決めをしておきましょう。
- 再委託の制限の遵守
- 無許可再委託の禁止:荷主から直接依頼された運送業務を、自社の許可なく他の運送事業者に再委託することは原則として禁止されています。やむを得ず再委託を行う場合は、適切な手続きを踏み、許可を得るようにしましょう。
- ドライバーへの教育・周知
- トラックGメンの役割と目的の周知:ドライバーに対して、トラックGメンがどのような活動を行い、何が是正の対象となるのかを説明し、理解を深めてもらいましょう。
- 情報提供窓口の周知:不当な要求や長時間労働があった場合に、社内外の相談窓口や情報提供先(トラックGメンなど)があることを周知し、ドライバーが安心して声を上げられる環境を整えましょう。
- 労務管理の見直し
- 就業規則の見直し:働き方改革関連法に対応した就業規則になっているか確認し、必要に応じて改定しましょう。特に、時間外労働の上限規制に対応しているか再確認が必要です。
- 給与体系の見直し:ドライバーの労働時間に応じた適正な賃金が支払われているか、手当やインセンティブ制度を含め、給与体系全体を見直しましょう。
荷主・元請け事業者がとるべき対策
荷主・元請け事業者様は、自社の物流が下請け運送事業者に過度な負担を強いていないか、以下の点を重点的に確認し、改善を図りましょう。
- 荷待ち・荷役時間の削減
- バース予約システムの導入:トラックが到着する時間帯を事前に予約できるシステムを導入することで、トラックの集中を避け、待機時間を削減できます。
- 荷役作業の効率化:荷役作業の標準化、フォークリフト等の荷役機器の導入、作業員の増員などにより、作業時間を短縮しましょう。
- 事前準備の徹底:荷物の仕分けや梱包など、荷役作業に先立つ準備を徹底し、トラック到着後の作業をスムーズに進められるようにしましょう。
- 荷役分離の検討:ドライバーが荷役作業を行う必要がないよう、荷役作業を専門の作業員に任せる「荷役分離」の検討も有効です。
- 適正な運賃・料金の支払い
- 書面契約の徹底:運送事業者との契約は、書面で交わし、運賃、料金、付帯業務、荷待ち・荷役時間の料金などを明確にしましょう。
- 運賃交渉の透明化:運送事業者に対し、一方的な値下げ交渉を行わず、燃料費や人件費の上昇分などを考慮した適正な運賃・料金を設定しましょう。
- 燃料サーチャージへの理解:燃料価格の高騰は運送事業者の経営を圧迫します。燃料サーチャージの導入や、その必要性について理解を示し、協議に応じましょう。
- 物流業務の効率化への協力
- 共同輸配送の検討:複数の荷主が共同で輸送を行うことで、積載効率を高め、トラックの台数を削減できる可能性があります。
- モーダルシフトの推進:長距離輸送において、トラック輸送から鉄道や船舶輸送への転換(モーダルシフト)を検討し、ドライバーの長時間労働の削減に貢献しましょう。
- パレット化・ユニットロード化:荷物のパレット化やユニットロード化を進めることで、荷役作業の時間を大幅に短縮できます。
- 社内体制の整備と従業員への周知
- コンプライアンス意識の向上:物流担当者や購買担当者に対し、トラックGメンの活動内容や関連法規、不適正な取引がもたらすリスクについて教育し、コンプライアンス意識を高めましょう。
- 社内相談窓口の設置:運送事業者からの相談や苦情を受け付ける窓口を設置し、迅速に対応できる体制を整えましょう。
- 「ホワイト物流」推進運動への参加
- 国土交通省が提唱する「ホワイト物流」推進運動は、トラックドライバーがより働きやすい環境を構築し、物流の安定化・効率化を図るための運動です。荷主企業としてこの運動に賛同し、自主行動計画を策定・公表することで、社会的な信頼を得ることができます。
トラックGメンと向き合い 持続可能な物流の実現へと
今回は、トラックGメンの活動と、特に10月・11月の集中監視月間に向けた対策について詳しく解説しました。
トラックGメンの導入・監視強化は、単なる取締り強化ではなく、「健全な物流のあり方を共に築く」ための取り組みです。
荷主・元請け・運送事業者がそれぞれの立場で責任を果たし、協力し合うことが、ドライバーの働きやすい環境と、持続可能な物流ネットワークの構築につながります。
未来の物流を支えるため、皆様と共にこの課題に取り組み、より良い業界を築いていけることを願っています。
不明な点や不安な点がございましたら、国土交通省の各地方運輸局にお問い合わせいただくか、行政書士 諸井佳子事務所までお気軽にご相談ください。皆様の事業を全力でサポートしてまいります。