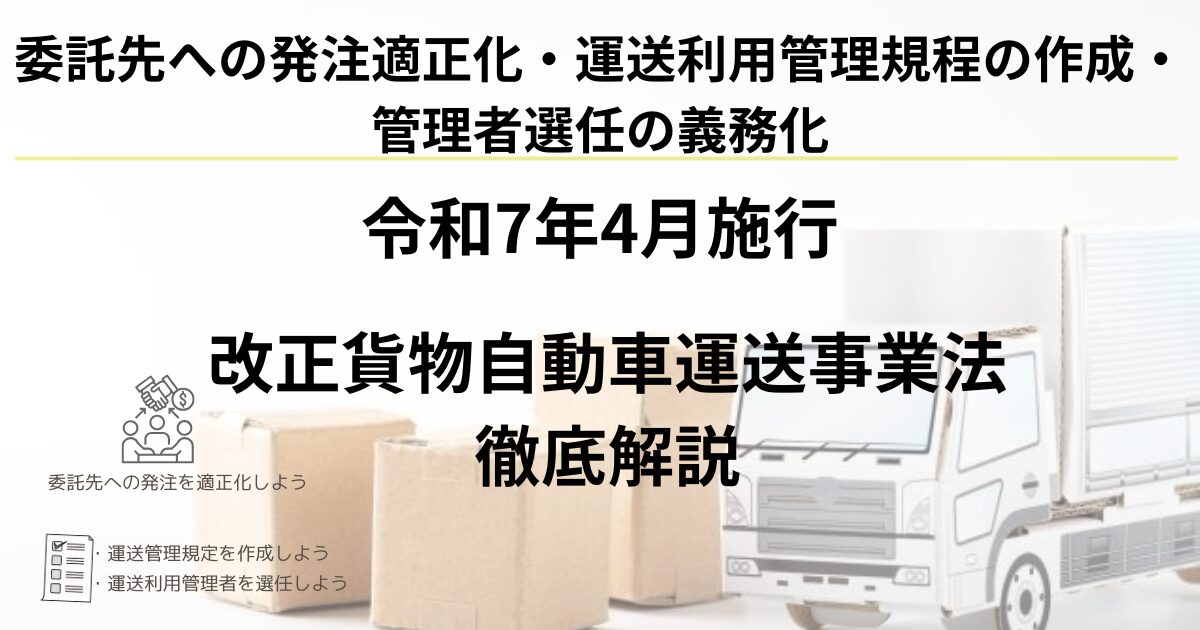近年、荷主と運送事業者間の取引においては、不適切な運賃や条件による下請け構造が問題視されており、運送事業者の経営を圧迫する要因の一つとなっています。このような状況を改善するため、委託先への発注の適正化(健全化措置)、そしてそれを推進するための運送利用管理規程の作成と運送利用管理者の選任義務化が、関連法規の改正等により強化・推進されています。
これらの措置は、運送事業者様の持続可能な経営に非常に重要なポイントとなります。今回は、これらの変更点について、具体的な内容や対応策を分かりやすく解説いたします。
健全措置化の努力義務について
利用運送を行うときには、ドライバーの働き方や運賃の適正化などを意識して、業界全体が健全になるように取り組んでくださいね、という“努力”が求められるようになります。
「こうしなさい」という“強制”ではなく、「できる限りこうしてくださいね」という“努力義務”です。でも、国としては今後の運送業界の健全化のためにとても大事なことだと考えているので、無視はできない内容になっています。
具体的にいうと、たとえば
- 荷主との契約内容をちゃんと見直して、無理な運送条件になっていないか確認する
- ドライバーが長時間働かないように運送計画を立てる
- 下請けの運送会社に対しても、適正な運賃で依頼する
運送利用管理規程の作成とその重要性
委託先への発注適正化を実効性のあるものとするためには、事業者が主体的に取り組むための社内ルール、すなわち運送利用管理規程を作成することが重要となります。
一定規模以上(前年度の利用運送料が100万t以上)のトラック事業者には2つの義務が課されます。
- 運送利用管理規程を作成し、国土交通省に届け出る義務
- 運送利用管理者を選任し、国土交通大臣に届け出る義務
運送利用管理規程とは、自社が他の運送事業者に貨物の運送を委託する際の手続きや判断基準、管理体制などを明確に定めたものです。
運送利用管理規程に盛り込むべき必要項目
①健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項
②健全化措置の内容に関する事項
③健全化措置の管理体制に関する事項
④運送利用管理者の選任に関する事項
自社の事業規模や特性に合わせて、実効性のある運送利用管理規程を作成することが重要です。必要に応じて、行政書士などの専門家のアドバイスを受けることも有効でしょう。
運送に関するご依頼は、運送業専門行政書士 諸井佳子事務所にお問合せください。
運送利用管理者の職務
委託先への発注適正化と運送利用管理規程の実効性を高めるために、一定規模以上の運送事業者には運送利用管理者の選任が義務付けられています。
運送利用管理者は、事業運営上重要な決定に参画する地位にある者(役員など)から1人選出します。
運送利用管理者の職務は以下のとおり
1)健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決定すること。
2)健全化措置の実施及びその管理の体制を整備すること。
3)実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当該実運送体制管理簿の作成事務を監督すること。
届出期限
利用運送料が100万トン以上となった年度の翌年度の7月10日までに届出をする必要があります。
例)令和6年度に100万トン以上となった場合は、令和7年7月10日が届出期限です。
【まとめ】今こそ、適正な運送体制づくりへの第一歩を

令和7年4月から施行される今回の改正は、単なる制度変更ではなく、運送業界全体の健全化に向けた大きな一歩です。特に委託先への発注の適正化や、運送利用管理規程の作成・管理者の選任は、運送事業者にとって、これらの取り組みはこれからの経営をより良い方向へ導くための大切なステップとなります。
努力義務とはいえ、適正な運賃の確保や働き方改革を進めるうえで避けて通れないポイントであり、自社の信頼性や持続的成長に直結する課題です。
- 発注条件を見直し、再々委託などの無理な構造を防ぐ
- 社内ルールを整備し、責任ある管理体制を確立する
- 国への届出など法令対応を確実に進める
これらの取り組みは、結果的に現場で働くドライバーの環境改善や適正な利益の確保につながり、業界全体の信頼回復にも寄与します。
「知らなかった」「対応が遅れた」では済まされない時代です。自社の規模や実態を正しく把握し、早めの準備を進めましょう。
制度への対応は、今後の競争力強化のチャンスでもあります。
取り組みの具体化に不安のある事業者様は、専門家のサポートを活用し、確実な一歩を踏み出していきましょう。
もし、運送利用管理規程やその他関連法規に関するご不明な点やご不安なことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。行政書士 諸井佳子事務所では専門的な知識と経験に基づき、皆様の事業運営を全力でサポートさせていただきます。