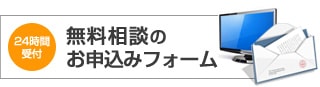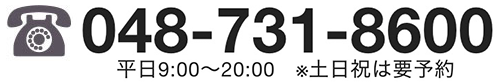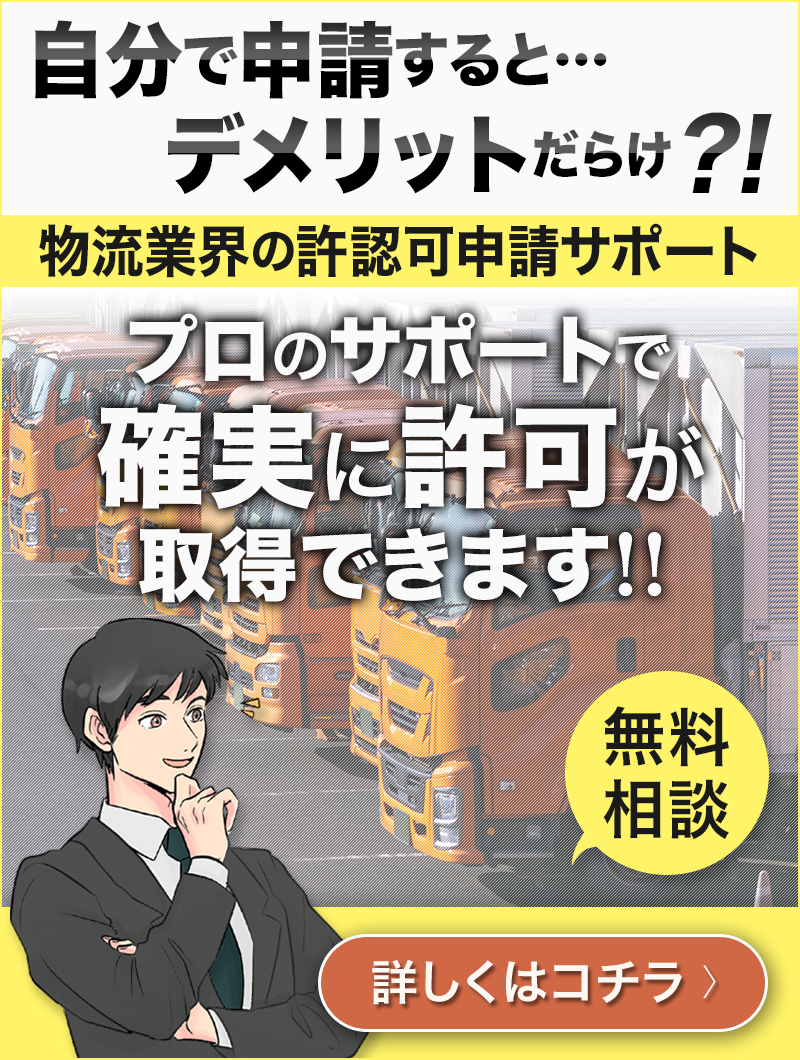運送業の営業所増設の手続き

運送業を始めて、順調にいけば、取引先や取引量が増えて営業所が少し手狭になっていくこともあるでしょう。
ただ、運送業を営んでいる人は営業許可を得る時にとても大変だったという記憶があるかと思います。なぜなら、地域によって規制が違うし、規制がとても多いからです。全て理解するのには時間と労力が必要です。
営業所を大きくする時にも、やはり厳しいルールがあります。
今回は、営業所の増設について詳しく解説します。
営業所の増設
営業所を増設する際には、運送業の経営計画が変更になったとして、地方運輸局へ営業所増設の認可申請をすることになります。
移転の場合と違って、人員要件や車両台数の要件が加わります。
この申請は、「一般貨物自動車運送事業の経営計画変更認可申請」といい、認可がおりるまでに1~4か月程度かかります。
増設はどのような時にする?
1.他の都道府県への進出
既に運送業を営む営業所として、地方運輸局に登録されている住所とは別の都道府県に進出し、営業所を設ける場合に営業所増設の認可申請をする場合です。
この場合、同時に駐車場の増設認可申請も必要となります。
2.拠点の増加(同一都道府県内)
現在、運送業の営業所として運輸支局に登録されている住所よりも、10㎞以上離れた場所に営業所を設けるため営業所増設の認可申請をする場合です。地域により距離の規制に違いがありますので、確認が必要です。
この場合も、営業所増設と同時に駐車場増設認可申請が必要になります。
条件
増設の前段階として、営業所の要件を確認しておきましょう。
①営業所と休憩施設が法に反しないこと(都市計画法、農地法、建築基準法等)
特に都市計画法の規定には注意してください。増設する営業所の場所が、市街化調整区域と呼ばれる場所ではないことが大前提となります。
詳しくは、別の記事に書いてあるので、参考にしてください。
営業所を増設する場合は、原則休憩施設も増設しなければなりません。
②使用権原があること
③建物と認められるものであること
④適切な規模であること
⑤休憩(仮眠)室があること
⑥車庫(駐車場)が適切な場所にあること
営業所増設をする際に、車庫も増設する場合は、車庫の設置の要件を満たすことが必要です。
|
・駐車場に車両すべてを駐車可能であること。 ・駐車場出入口前の道路の幅が、基本的に5.5m以上あること(一方通行の場合は3m以上)。 ・駐車場の出入口が交差点の角、踏切、交差点、横断歩道の近くにないこと。 ・駐車場の近隣に幼稚園や小学校など児童の行き交う施設がないこと。 |
などが条件となります。
⑦人員が確保できていること
ドライバーが5人以上、資格のある運行管理者を1人以上確保できていること。
自動車整備士資格3級以上、または運送会社で、整備管理者などの実務経験のある整備管理者を1人以上確保できていること。
この人たちは、申請時にまだ雇用契約を結んでいなくても、認可取得までに雇用することが決定してれば大丈夫です。
⑧5台以上の車両があること
増設する営業所所属の車両が少なくとも5台はなければなりません。注意が必要なのは、5台の中に軽自動車を含むことはできない、ということです。
必要書類
|
・営業所の賃貸借契約書と車庫の賃貸借契約書の写し、又は登記事項証明書 ・周辺地図 ・営業所、休憩室、車庫の平面図と写真 ・車検証の写し ・運行管理者、整備管理者の資格証の写し ・宣誓書 |
などが必要です。必要書類は、同一県内であるか、他府県であるかによって異なってきます。
プレハブ、トレーラーハウスは?
プレハブなどの簡易な建物や、トレーラーハウスを運送業の営業所や休憩室として登録することは可能です。
ただし、市街化調整区域の場合は、基本的にプレハブを運送会社の営業所として使用できません。トレーラーハウスは市街化調整区域であっても、唯一、運送業の営業所として使用することが可能です(一部地域を除きます)。
増設ならではの注意事項
運送業の営業所増設のときに3つ気を付ける点があります。
【1】NOX・PM規制適用外の地域で使用しているNOX・PM不適合車を、NOX・PM適用地域には持ち込めません。
いわゆる排ガス規制です。車検証の備考欄に、適合しているか、排出基準への可否と使用可能最終日などが記載されているので、確認することが必要です。
【2】元の営業所を廃止して増設の場合、元の営業所で選任した運行管理者と整備管理者は解任することとなります。そして、増設した新しい営業所には、常駐する運行管理者を改めて置き、運行管理補助者も必ず一人おくことになります。
【3】営業所増設の場合は、運送業許可を新規取得する場合と違い、残高証明書の提出は不要です。
まとめ
今回は、運送業の方が営業所を大きくしたい、増やしたいときに守らなければならないルールについて解説しました。
不動産を見に行って、たくさんの法令を調べ、資料を集める必要があるため、かなりの労力と時間を要します。また、地域によって規制も異なってきます。
資料収集や提出、調査などについては専門家である行政書士までお気軽にお問合せください。