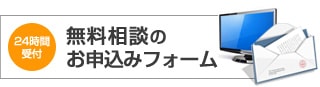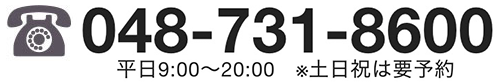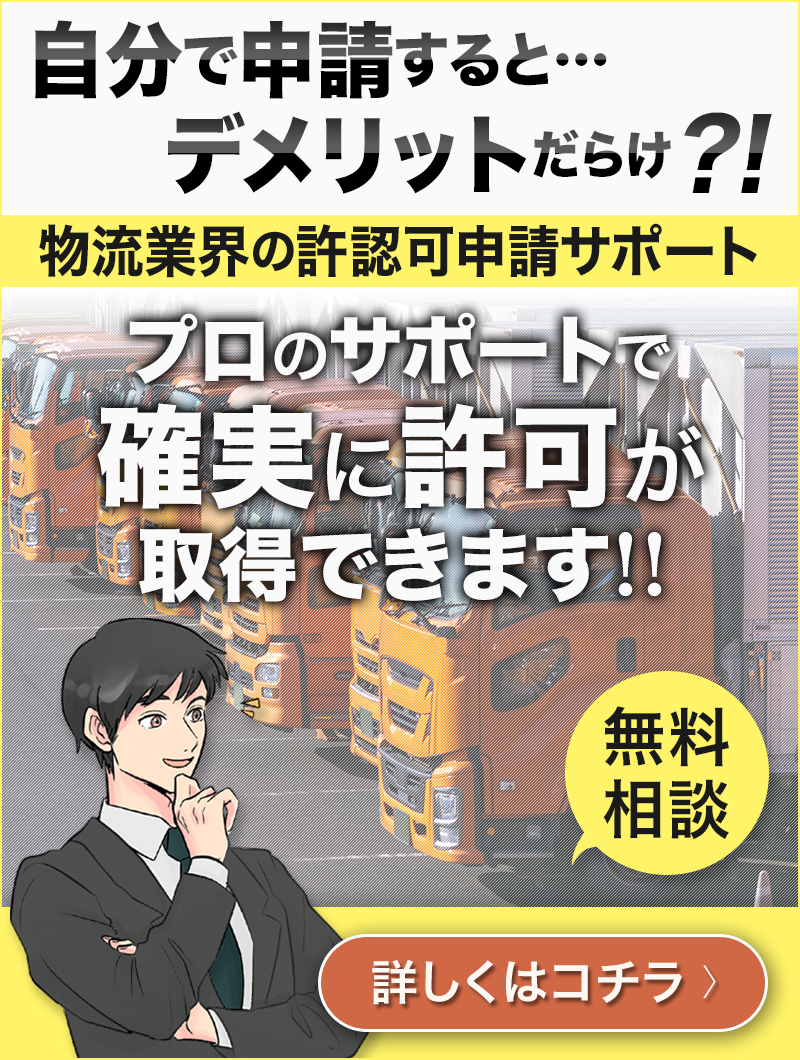運送業の車庫までの距離について解説

運送業を営む上で重要なのは、車庫(駐車場)の存在です。細かい要件が定められており、すべて満たさないと車庫として利用することができなくなり、営業することができなくなってしまいます。
大きなトラックで、しかも複数台もあると、駐車場を探すのに骨が折れる、という人も少なくありません。
運送業をする上で、しっかり要件などを知っておく必要があります。
具体的には、営業所からの距離、車庫内の広さ、車庫の前面道路、使用権原、区画の明確性法令遵守ということが最低限満たしていなければなりません。
今回は、マストの要件のひとつである運送業の車庫までの距離について詳しく解説いたします。
営業所からの距離
車庫(駐車場)は営業所に併設するものであることが原則です。
ただし、土地の状況などから、併設できない場合も当然あります。このような場合は、各運輸局別に定められた距離以内であればよしとされています。
具体的には、関東運輸局管内は、2つに区分されていて、
・東京23区、横浜市、川崎・・・20キロメートル以内
・その他の関東及び山梨県・・・10キロメートル以内
と規定されています。
20キロメートルであれば、だいぶ見つけやすいかもしれませんが、全国で、5キロメートルから20キロメートルと幅があるので、チェックしましょう。
距離の測り方
営業所と車庫の距離は、上記のとおりですが、この距離はどうやって算定するのでしょうか。
私たちは、地図を見て目的地に向かう時、歩く全ての道を距離として数えて、曲がったり折り返したりしながら目的地に到着します。これを実距離といいます。
しかし、今回の距離とは、実距離ではなく、「直線距離」で測ります。つまり、歩く道ではなく、スタート地点とゴール地点を定規でまっすぐ線をひいた、その線の距離を測ればいいのです。
そうすると、多くの場合、実距離より短くなります。営業所と車庫の距離が、車のナビで13キロメートルと表示されても、場合によっては10キロメートル以内ということもありますので、必ずチェックしましょう。
越県する場合は?
東京都の江戸川区に営業所があり、車庫が千葉県に位置する、という場合も当然あります。このような場合は、少し悩むと思います。
先ほどの説明だと、東京都の23区は20キロメートル以内とされ、千葉県は10キロメートル以内とされているからです。
このような時は、営業所がある地域に従うことが原則です。したがって、営業所が23区にあるので、千葉県の車庫まで20キロメートル以内であればよいとされます。ただし、このような越県する場合は、県によって異なる扱いをするところもあるので、運輸局に問い合わせることをお勧めします。この時、営業所がある県の運輸支局に行くことを忘れないようにしましょう。
点呼
営業所と車庫が離れてしまうと、点呼に困る場合があります。
点呼とは、ドライバーの体調管理、トラックの整備状況などをチェックして事故を防ぐためのもので、正しく確実に行うことが義務づけられています。これを怠ると、罰則もありますが、しっかりと習慣づければドライバーはもちろん、会社を守ることができます。(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第17条など)
対面点呼、電話点呼、IT点呼の3種類があります。そして、点呼を行い、確認事項を記録しなければなりません。
点呼執行できる場所は、原則、認可を受けた営業所と車庫です。隣接している場合や同じ敷地にあれば、簡単にできますが、距離がある程度離れてしまう場合には、点呼方法が異なります。
この場合の方法は3つあります。
①車庫で「日常点検」を行い、営業所まで自家用車で行き、整備管理者に運行の可否を受ける。営業所で運行管理者から点呼を受けて、自家用車で車庫へ戻る。
自家用車で往復することになるので少し面倒な気もしますが、営業所と車庫の間を、点呼なしでトラックを運転することを避けるために行います。
②運行管理者が車庫に行き、点呼を行う。
簡単ですが、もしあちこちに車庫がある場合、運行管理者は少し大変かもしれません。
③IT点呼をする。
認可営業所、認可車庫間では、一定の条件を満たせばIT点呼をすることができます。この時、Gマークは必要ありません。ただし、この条件は、巡回指導で一定の高評価を得た上で国に届出をすることが必要なので、すぐには行うことができないことを覚えておきましょう。
まとめ
今回は、運送業の方が必ず使う車庫の距離制限について解説しました。
事業用の車には厳しい制限が設けられているため、法令に遵守した形で許可を得て営業しないと罰則の対象となります。
運輸局に問い合わせたり、距離を測り、届出をしたり、手続には少し面倒なものがあります。リスク回避及び運輸局に行き面倒な手続を迅速に進めるためにも、専門家である行政書士までお気軽にお問合せください。