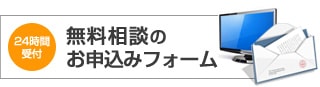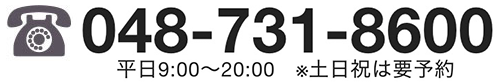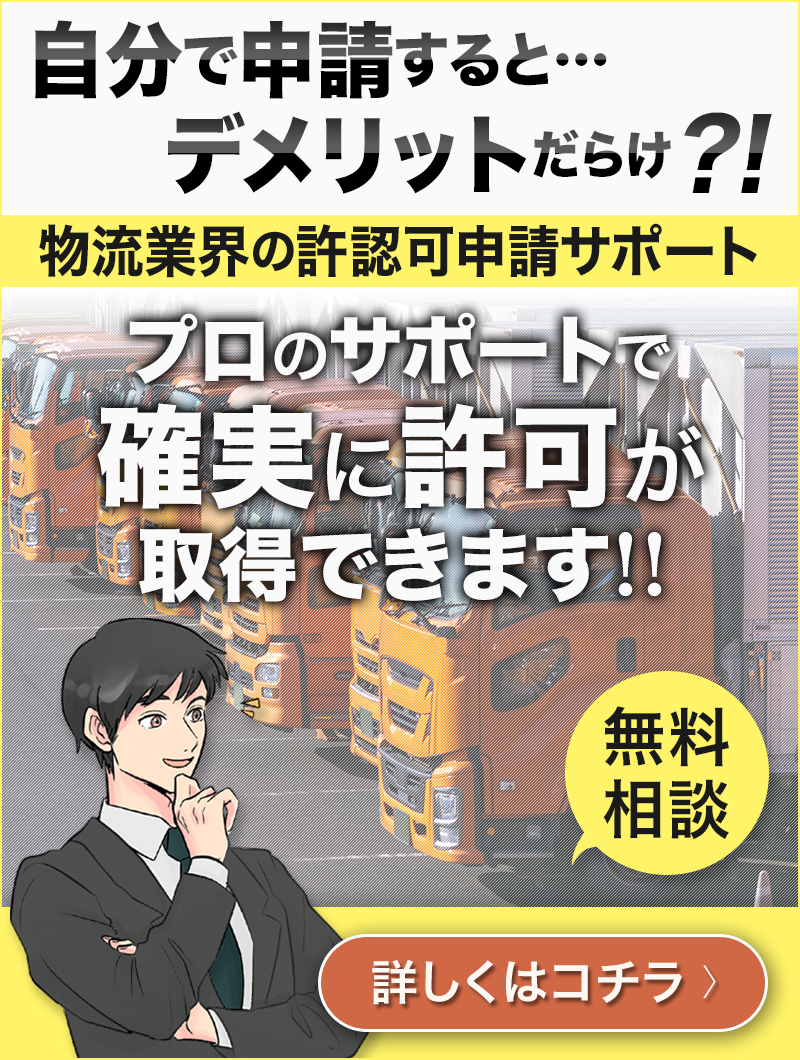整備管理者と整備主任者の違いについて解説

自動車を使用するような事業を行っていると、整備管理者や整備主任者というような名前を聞くことが少なくないと思います。
しかし、名前が似ているこの2つの仕事はどこが違うのか、と聞かれるとはっきりとは答えられない、どちらが自身の事業所に必要なのか困っている、というような事業者様もいるかもしれません。
こちらでは、そのような方に向けて整備管理者と整備主任者の違いについて、仕事内容と資格要件という2つの観点から解説していきます。
整備管理者とは
整備管理者とはその名の通り、整備を管理するという役割を担います。自動車を使用する場合、整備は不可欠です。そのため、一定以上の自動車を使用する事業はすべて整備管理者を選任する必要があります。
では、整備を管理するとはどういうことなのでしょうか。事業で使用する自動車を実際に点検するのは、個々のドライバーです。そのため、会社全体の安全性は、個々のドライバーがきちんと点検を行っているかどうかにかかっています。それなのに、万が一ある1人のドライバーが点検業務を怠り事故を起こした、となれば、会社全体の信用は失われてしまいます。このような事態を防ぐためにも、整備管理者は、きちんと点検が行われているかを確認し、その結果に基づいて安全な車両だけを走行させます。具体的な業務は、日常点検の方法決定・実施、定期点検の方法決定・実施、点検結果に基づく必要な整備の実施、記録簿の管理、自動車車庫の管理、ドライバー・整備員への指導などです。
つまり、「一定以上の自動車を使用する事業所で」「点検が正しく行われるようにする」のが整備管理者です。
整備管理者の資格要件
整備者になる方法は2通りあります。
①資格による選任
自動車整備士技能検定を合格し、国家資格である整備士資格を取得した方は整備管理者に選任できます。この場合、実務経験は必要ではありません。
②実務経験による選任
※二輪を除く整備管理をする自動車の点検・整備・整備管理・に関して2年以上の実務経験をもつ
※地方運輸局が主催する研修(整備管理者選任前研修)を修了
以上の2点の条件を満たしている方は整備管理者に選任できます。
整備主任者とは
整備主任者の仕事内容について説明します。
簡単に言うと、整備主任者とは自動車を整備する際の分解作業が、国の基準を満たしているかを確認する業務です。
そのため、整備主任者を選任する必要があるのは、自動車整備工場ということになります。正確には、自動車整備工場が国の認定を受け、認証工場や指定工場となる場合、その事業所には1名以上の整備主任者を選任する必要があります。
具体的な仕事内容としては、分解整備の管理のほかにも、分解整備記録簿の記載・保存なども行います。Buン回整備記録簿とは、車検の時に自動車のどこを点検修理したかを記します。車のカルテのような役割を担うため、非常に重要な業務のひとつです。
まとめると、整備主任者とは「国が認定した自動車整備工場で」「分解整備が正しく行われるようにする」という仕事です。
整備主任者の資格要件
整備主任者になるには、以下の3つの条件すべてを満たす必要があります。
1.1級自動車整備士もしくは2級自動車整備士の資格を保有している
(ただし、分解整備の対象がエンジン部分も含む場合、2級自動車シャシ整備士は不可)
2.所属している事業所から選任され、各都道府県の運輸局に届出て受理されている
3.自動車整備主任者研修を受講している
上記条件のうちどれか1つではなく、すべて満たさなければならないという点に注意しましょう。
まとめ
今回は、名前がよく似た2つの仕事、整備管理者と整備主任者についてその違いを解説いたしました。
まとめると、仕事内容の観点では、前者は一定以上の自動車を使用する事業者で点検業務を管理する一方、後者は国が認定した自動車整備工場で分解整備を管理するという違いがあります。
資格要件の観点では、前者は整備士資格か実務経験いずれかがあれば選任できますが、後者は整備士資格や研修など、すべての条件を満たさなければ選任できません。
このように、名前こそ似ているものの、整備管理者と整備主任者は全く違う仕事です。もし、事業者様がどちらを設置すればよいかわからないと困っていましたら、上記の違いをもとに、今一度ご自身の事業にはどちらが必要なのかを確認してみましょう。
確認しても不安だな、違いがよくわからないなという方は専門家である行政書士までお気軽にご連絡下さい。