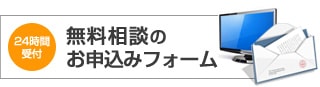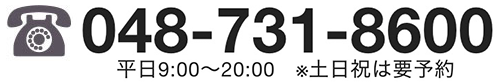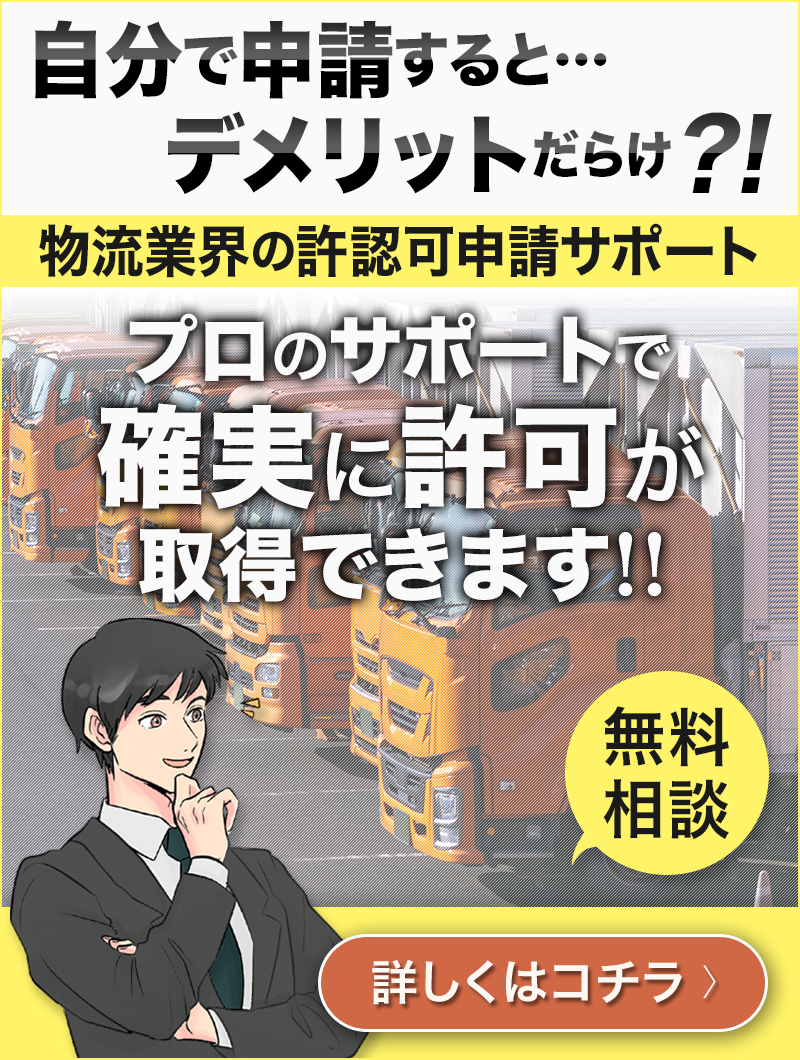トップページ > 一般貨物自動車運送事業許可 > 一般貨物自動車運送事業許可の緑ナンバーとは?
一般貨物自動車運送事業許可の緑ナンバーとは?

緑ナンバーはタクシーで見かけたことがあると思います。
では、一般貨物自動車運送事業許可の緑ナンバーとはどのような意味を持つのでしょうか。
1 緑ナンバーとは
緑ナンバーは緑色地に白色の文字で、事業用の車に取り付けられており、別名「営業ナンバー」と言われています。
ちなみに、白ナンバーはご存知のように白地に緑色の文字で、普通サイズ以上の自家用車に取り付けられています。
黄色ナンバーは、黄色地に黒色の文字で、軽自動車サイズの自家用車に取り付けられています。
黒色ナンバーは黒色の地に黄色の文字で、軽自動車サイズの営業車を表すプレートです。
青ナンバーは都心部でたまに見かけますが、青色の地に白色の文字で書かれたプレートのことをいいます。これは、外交官が利用する外務省用車に取り付けられています。
ここまで読んで、「あれ?緑ナンバーは事業用の車に取り付けられているというけど、白ナンバーのトラックも見たことあるけど?」と思われる方もいると思います。
緑ナンバーと白ナンバーのトラックの違いは、運搬料金をもらって他社の物品又は人を運搬するかどうかという点にあります。
つまり、緑ナンバーは運搬を事業として行っている場合に取り付ける義務があるナンバープレートということになります。
2 緑ナンバーのメリット・デメリット
では緑ナンバーの場合、どのような優遇措置があるでしょうか。
メリットの一つは、都道府県税の自動車税の優遇があります。
最大乗車定員が3人以下のトラックを例にとってみると、積載量4トン超〜5トン以下なら白ナンバーだと年間25,500円ですが、緑ナンバーでは18,500円となっています。
積載量7トン超〜8トン以下であれば、白ナンバーでは40,500円であるのに対し、緑ナンバーでは年間29,500円と3割近く安くなっています。
また、国税である自動車重量税も緑ナンバーの方が安くなっています。緑ナンバーでは、車両総重量4トン超〜5トン以下なら年間13,000(本則税率)円、車両総重量8トン超〜9トン以下ならば、23,400(本則税率)円がかかります。一方、白ナンバーでは車両総重量4トン超〜5トン以下なら20,500(本則税率)円、車両総重量8トン超〜9トン以下なら、36,900(本則税率)円がかかり、白ナンバーは緑ナンバーに比べ収める税金は高くなっています。
税金以外のメリットとしては、緑ナンバーは厳しい条件をクリアして初めて取得できるナンバーなので、企業を始めとしたお客さんの信用度は上がります。
また、公共事業も請け負うことができ、営業規模は大きくなります。
さらに、緑ナンバーを取得時には、その事業者は従業員の社会保険ならびに雇用保険加入義務が発生するので、福利厚生が向上する結果、人材確保が有利になります。
一方で、緑ナンバーのデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。
一つは、自賠責保険料が増加します。2トン超のトラックの場合、白ナンバーが22,570円であるのに対し、緑ナンバーになると30,530円になってしまいます。
また、緑ナンバーになると従業員の給与は消費税控除対象経費にならなくなります。そのため、白ナンバー時に比べて消費対象経費が減少し、消費税の支払いが増加するというデメリットがあります。
3 緑ナンバー取得条件
①申請者や会社の役員が1年以上の懲役又は禁錮を受けてから5年経過していないなどの欠格要件に該当しないこと
②運送事業に専従する常勤の役員うち1名が法令試験に合格すること
③必要な有資格者を配置すること
営業所ごとに、定められた人数の「運行管理者」、「整備管理者」を配置しなければなりません。
④必要な人数の運転者を選任すること
営業所ごとに使用権限を有する車両を5両以上有し、運転者も5名以上必要になります。常時選任運転者はトラックの台数以上雇わなければいけません。
⑤営業所が確保されていること
建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していない営業所が必要です。
⑥休憩・睡眠施設があること
睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり2.5平方メートルの広さを有することが必要です。
⑦営業所に併設または一定の距離内に、全車両が収容できる車庫があること
営業所に併設することが原則ですが、併設できない場合は一定の距離内に、一定の間隔を取って全車両が収容できる車庫を置く必要があります。
⑧必要な数の車両数があること
営業所ごとに、運行に必要な車両を5台以上確保することが必要です。
⑨所要資金
所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が次により算定した所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であることが求められます。
例えば、人件費・燃料費・油脂費・修繕費の6ヶ月分の運転資金、自動車重量税、自動車税、保険料各1年分を所要資金として算出します。
⑩所要資金の常時確保
所要資金の全額以上が、申請日以降常時確保されていることが必要です。
⑪損害賠償能力
100両以下の自動車で事業を行う場合は、「対人無制限・対物200万円以上」の任意保険に加入する必要があります。
以上の要件をクリアし、申請をすることで緑ナンバーを取得します。