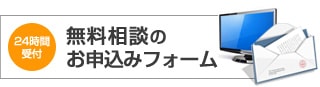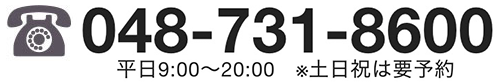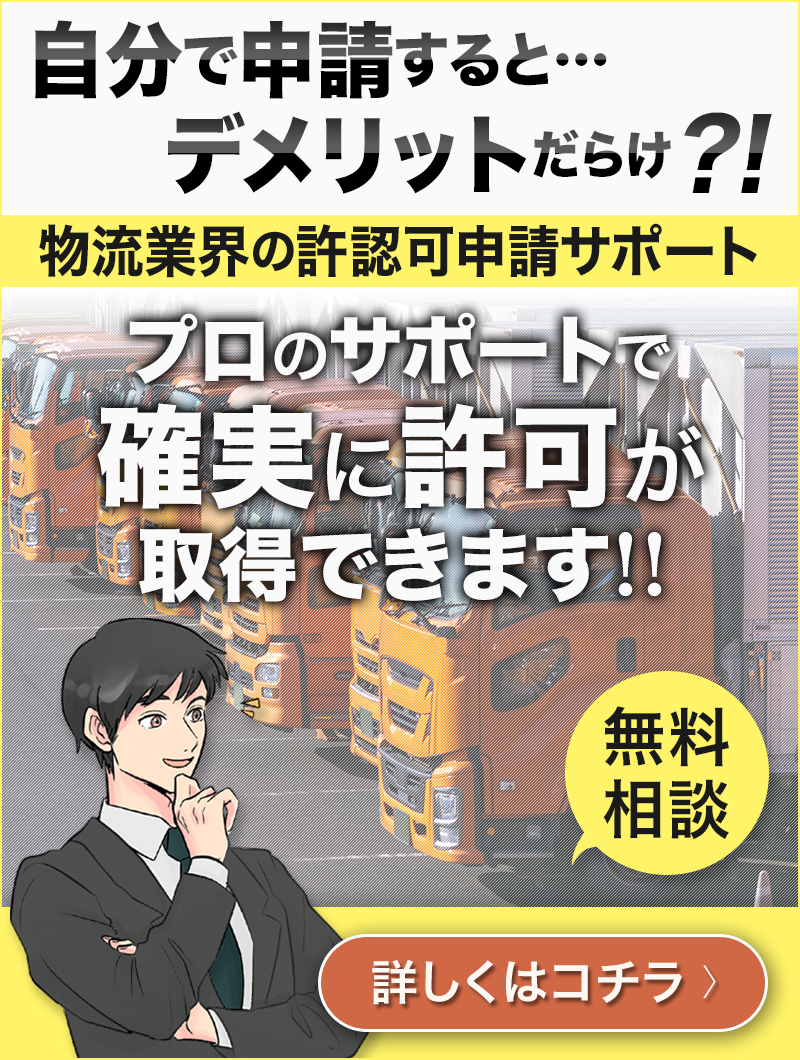運送業の車庫飛ばしとは?

運送業を営む上で重要なのは、何が重要かご存知でしょうか。そう、法令遵守です。
貨物自動車運送事業者に法令違反があると、色々な強さの行政処分がなされます。厳しいと車両や駐車場(車庫)に使用禁止、事業の全部又は一部の停止処分、許可の取り消し処分などがあります。軽いものですと、警告、勧告があります。
行政処分は、違反点数が加算される形で管理され、事業者ごとに管轄区域単位で3年間累計されます。3年間の合計点数が一定数以上だと、事業の停止などの厳しい処分が科されます。
違反の種類によっては、繰り返し同じ違反をした場合に許可取り消しとなることもあります。
法令違反の一つに「車庫飛ばし」というものがあります。こちらでは、車庫飛ばしの法令違反をしてしまわないように、運送業の車庫飛ばしとはというテーマで詳しく解説いたします。
「車庫飛ばし」とは
一般的に「車庫飛ばし」とは、使用の本拠地で車両を使用していないということをいいます。
車両を手に入れた時に必ず必要となる資料に、「車庫証明書」があります。持っている車を止めるところがなければ、車両の適切な管理ができないためです。
この車庫証明書を取得するには、「使用の本拠の位置から2キロメートル以内に保管場所を設けること」が必要となり、その保管場所を管轄の警察署へ届け出ればいいのです。
新しい車を手に入れた時に、最も手間がかかり、大切な過程だと言えます。
このことは、事業用の車に限らないので、知っている方は多いかと思います。
そして、この車庫証明書に記載した「使用の本拠の位置」で車両を使用していなければ、車庫飛ばしとなります。
よくあるのは、引っ越しした後に、登録の変更をせずに以前の住所のままの車を新しい家に持ってきたケースです。登録を変更しなければ、わざとではなくても、「車庫飛ばし」に該当してしまいます。
また、やってしまいがちのケースで、実家に車庫があり、そこで車庫証明を取得し、別の自宅で車両を使用する場合、これも「使用の本拠の位置」で車両を使用していないことになりますので、車庫飛ばしとなります。
そのため、できるだけ早くに「使用の本拠の変更」をして新しく車庫証明書を取得することをおすすめします。
事業用トラックの場合の「車庫飛ばし」
事業用トラックは、車庫から出発して、登録の車庫(駐車場)に戻ることが原則となります。
出発前と業務終了時に、点呼が義務づけられており、車両の日常点検も義務となっています。例外としてIT点呼、中間点呼や運行指示書でよいとされる場合もあります。
個人タクシーのように、車庫から出て運送業務に出て、自宅に直帰することは、認められていません。これは、自宅は、先ほどの「使用の本拠の位置」ではないからです。
事業用の車両は、ナンバープレートの色が緑です(グリーンナンバー)。だから、近隣の人や同業者は一見して判断できてしまいます。そのため、本来停める場所でないところに停めるのは、絶対に辞めましょう。
排ガス規制に適合しない車両の車庫飛ばし
最も問題となっているのが、ディーゼル車の登録のために行う「車庫飛ばし」です。
首都圏では、条例により「排ガス規制に適合しない車両」は登録・運行できません。東京都では、平成15年10月から実施され、平成18年4月に規制の基準値が強化されました。東京都環境確保条例で定める粒子状物質排出基準を満たさない車は、東京都内の走行を禁じられています。
この規制を回避するために、複数台トラックを所持する規制対象地域の事業者が、規制にかからない場所に住所を移転したように見せかけて車庫証明を取得する、ということが行われています。
これができてしまうと、登録は別の地域なので、東京をはじめとする規制対象の首都圏内で運行することができてしまうのです。そして、登録していない都内の車庫に停める、という非常に悪質といえる業者もいます。
ディーゼル車の規制は、各自治体に問い合わせてみてください。
刑罰はあるの?
車庫飛ばしは、公正証書原本不実記載等の罪にあたります(刑法第157条)。あまり聞いたことのない犯罪かもしれません。簡単に言うと、公的な資料に嘘の記載をする罪です。
この罪は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
特に、事業として運送業を営み、故意で虚偽の申告をした場合は、悪質と判断され、罰則が重くなります。
引っ越してバタバタしていたため届出を忘れていた、というような場合は軽い罰則になりますが、早くに行動するに越したことはないでしょう。
まとめ
今回は、運送業の方に注意してもらいたい車庫飛ばしについて解説しました。
事業用の車には厳しい制限が設けられているため、物件を見つけることも大変な場合があります。
そのため、車庫探しを後回しにしまいがちです。新しい登録や、たくさんの制限を確認することはかなりの労力と時間がかかります。
効率よく運送業を営むための確認及び申請などは、専門家である行政書士までお気軽にお問合せください。