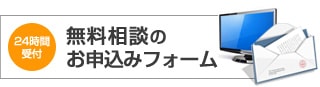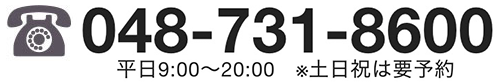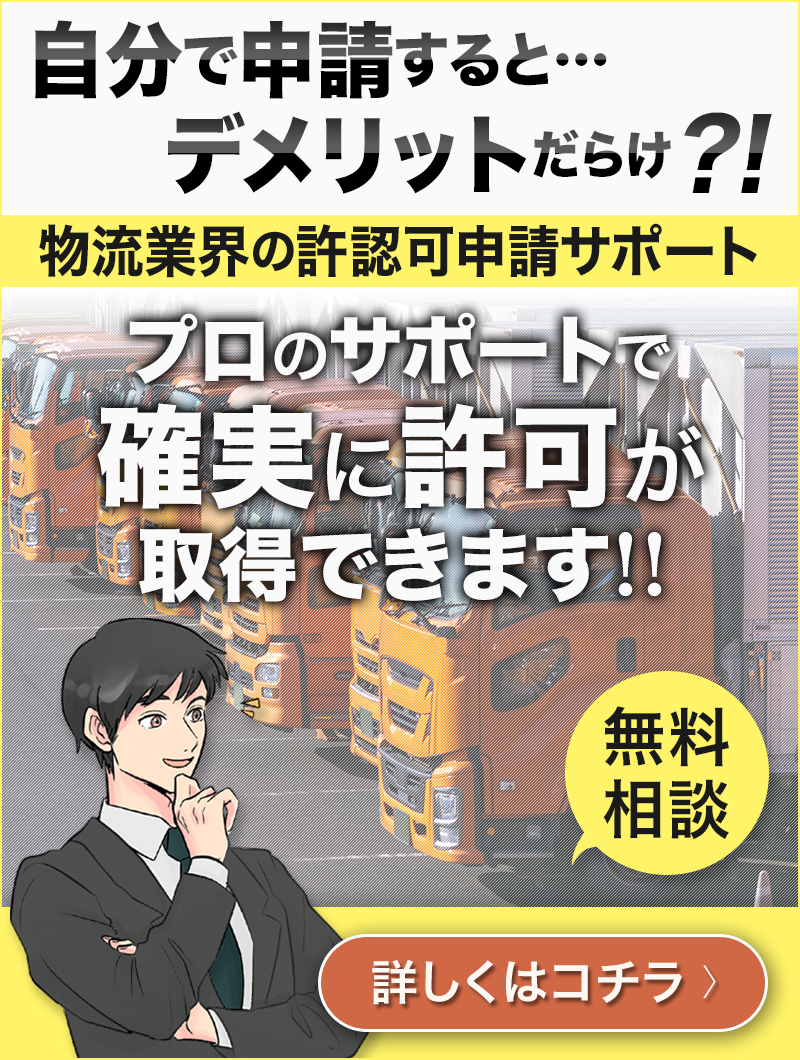運送業許可申請受付から運送業開業までの流れ

運送業の許可を取得後すぐに開業したいと思っているが、運送業はその後も様々な手続きがあると聞いた。許可を取得してから一体どのくらいで開業することができるのだろうか?
このように、開業に向けて様々な疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
運送業は飲食業などと異なり、許可を取得後すぐにスタートできるものではありません。
ですので、申請を行ってから開業までの流れを事前に把握しておくことが大切です。
そこで今回は、運送業許可申請受付から運送業開業までの流れというテーマで、詳しく解説致します。
開業までにどのくらいかかるの?
まず初めに、運送業の許可を申請してから開業できるまでにかかる期間は、どんなに早くても5ヶ月前後と言われています。
なぜこんなにも時間がかかるのでしょうか?
まずは大きな要因として運送業の許可を認可する運輸局が、審査を行う期間として4〜5ヶ月かかりますと発表しています。
ということは、許可の申請を行ってから許可が下りるまでに最低でも4か月は必要です。
審査が終えるのを待つだけなら良いのですが、その間に様々な試験や手続きを行う必要があるのも運送業許可の特徴です。
それでは、どのような流れで開業まで進めていくのかを次項で詳しく解説致します。
申請から開業までの流れ
開業までに必要な流れを1つずつご説明します。
1.地方運輸支局へ申請書類等を提出
必要書類を揃えて、運輸局へ提出しましょう。
2.運輸局側で審査を行う
地方運輸支局が審査を行います。結果が出るまで4〜5ヶ月は必要です。
その間、開業に向けて行える手続きが下記の3〜5です。
3.法令試験を受ける
申請後、結果を待っている間に法令試験を受ける必要があります。
奇数月にしか実施していないので、できるだけ早めに試験を受けましょう。
また不合格が2回続いてしまうと、一旦申請は取り消されてしまいますので、合格できるように勉強もしっかりと行う必要があります。
4.2回目の残高証明書の提出
申請後、約2か月後に運輸局から2回目の残高証明書を提出するよう通知がきます。
必要な資金が確実に確保されているかをチェックされます。
初回の残高証明の金額を下回っていると認めてもらえませんので、気をつけましょう。
金融機関で残高証明書を発行してもらい、期限内に提出しましょう。
5.社会保険等に加入
法人の場合、従業員や役員全員が社会保険等に加入しておくことが必須です。
健康保険だけでなく、厚生年金・労災保険・雇用保険への加入も必要です。
許可を取得後、従業員の保険加入の証明書を提出しなければならないので、必ず必要な手続きです。後回しにせず早めの手続きをお勧めいたします。
6.許可取得の通知が来る
運輸局の審査が終了したら、許可取得の通知が来ます。
7.交付式に参加・許可取得
運送業の許可を交付してもらうために、地方運輸支局が行う交付式に参加します。
大体、通知が来てから1週間以内に行われます。
許可取得後、提出する書類の説明や法令などの説明が行われますのでしっかりと確認しておきましょう。
8.登録免許税の納付
許可を取得した日から1か月以内に、登録免許税12,0000円を金融機関で納めましょう。
9.選任届の提出
運送業を行うにあたって必ず必要な“運行管理者”と“整備管理者”を、選任届という書類で運輸支局へ提出します。
10.運輸開始前届を提出
運輸開始前届に必要な書類を集めて、地方運輸支局へ提出します。
この際に、従業員が社会保険等に加入した証明なども必要なので準備しておきましょう。
11.連絡書の取得(車庫証明)
“事業用自動車等連絡書”というものが運輸支局で発行してもらえます。
この書類は、一般的なもので例えると車庫証明のようなものです。
12.緑ナンバーに変更
運送業で使用する車両のナンバーを、営業ナンバー(緑ナンバー)に変更して新しい車検証を取得しましょう。
また自動車任意保険への加入も必要ですので、手続きを行いましょう。
13.運輸開始届・運賃料金設定届
新しくした自動車任意保険の保険証券の写し・車検証の写しなどを運輸開始届と一緒に提出します。同時に運賃料金設定届も提出しましょう。
14.開業
全ての手続きが終えると、晴れて開業することができます。
15.巡回指導
開業してから6か月以内に、適正化事業実施委員会による巡回指導が行われます。
この際に5段階評価で評価されるのですが、評価がD〜Eになってしまうと行政処分となりますので、日々の点呼簿や日報・帳簿など必ずつけておくことが大切です。
以上が申請を行ってから開業までに必要な流れになっております。
様々な手続きが必要になるので、事前に流れを把握しておくことが大切です。
まとめ
今回は、運送業許可申請受付から運送業開業までの流れについて解説致しました。
運送業は許可申請を行って終わりではなく、開業するまでには様々な手続き等が必要になってくることが分かりましたね。
開業をいち早く行いたいと思っている方は、開業までに必要な期間を逆算して計画を立てながら手続きを進めていくことが大切です。
しかしながら日々お忙しい運送業の方にとって、これらの手続きを全てご自身で行うにはかなりの時間を要してしまう。とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、代行申請の専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。