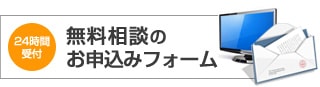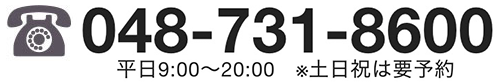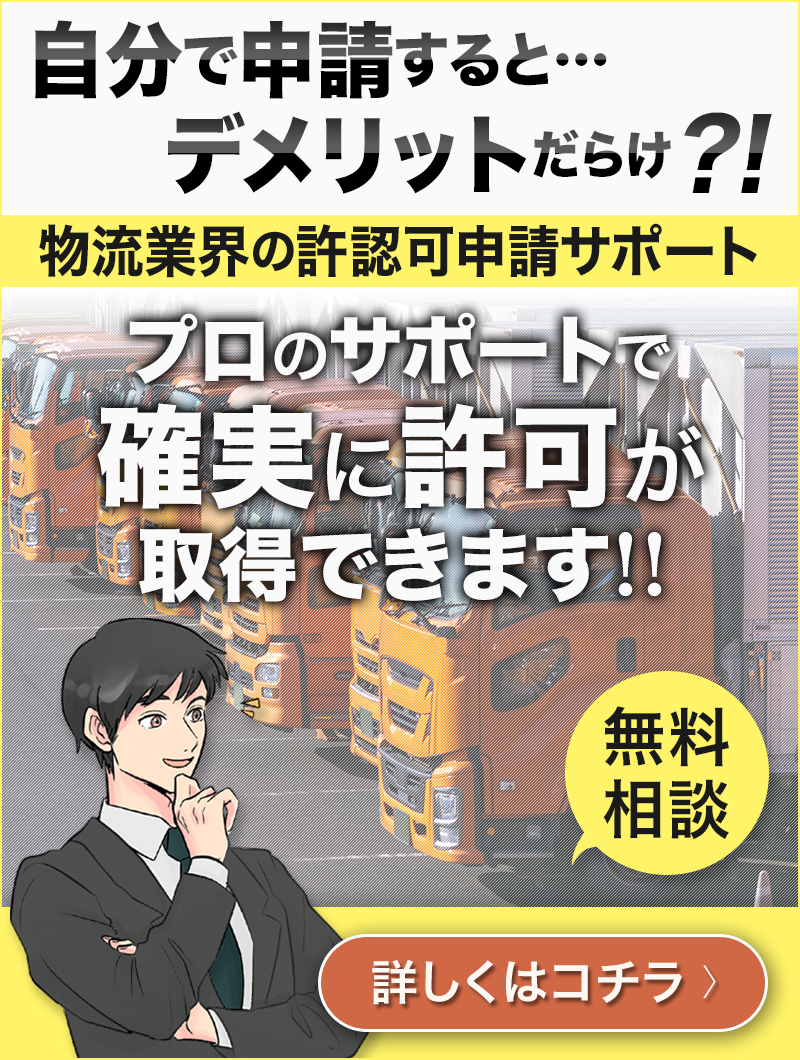運送業の車庫の前面道路と幅員について解説

運送業を営む上で重要なのは、車庫(駐車場)の存在です。細かい要件が定められており、すべて満たさないと車庫として利用することができなくなり、営業することができなくなってしまいます。
大きなトラックで、しかも複数台もあると、駐車場を探すのに骨が折れる、という人も少なくありません。
運送業をする上で、しっかり要件などを知っておく必要があります。
具体的には、営業所からの距離、車庫内の広さ、車庫の前面道路、使用権原、区画の明確性法令遵守ということが最低限満たしていなければなりません。
今回は、マストの要件のひとつである運送業の車庫の前面道路と幅員について解説について詳しく解説いたします。
幅員は、事前にちゃんと確認しないと、せっかく借りられたのに、使用予定の車両の車幅に対して幅員が足りずに使用許可がおりない、ということがありますので、注意しなければなりません。
車庫の前の道路の広さ
車庫の出入り口が面している前の道路を「前面道路」といいます。
前面道路は、車両が車庫への出入りに支障のないものであることが必要なのは、すぐわかるかと思います。
これは、大きなトラックが出入りする際、道が狭いと何度も切り返すことになり、交通の安全が損なわれることを避けるために車両制限令という法律で、道路の幅と出入りする車両の大きさに一定の制限がされています。
車両制限令のルール
車両の幅≦(道路幅員-0.5)/2 が原則です(車両制限令 第5条)。
ただし、交通量の量や相互・一方通行などでこの計算は変わりますので、この条文をしっかり読むことをお勧めします。
他の細かい条件について、以下で説明します。
前面道路が公道の場合
公道とは、県道や市道などをいいます。
この場合、出入り口の前の道路との関係において原則、「道路幅員証明書」により車両制限令に抵触しないものであることを証明すること、とされています。つまり、必要な条件は、前面道路の幅が下記の長さ以上あることです。
具体的には、
相互通行の場合
2トンクラスで5メートル以上、4トン・大型車クラスで5.5~6メートル以上
一方通行の場合
2トンクラスで2.5メートル以上、4トン・大型車クラスで3m以上
とされています。
ただし、市街地道路、市街地外道路、歩行者の数がどのくらい多い・少ない、使用する車両の幅によって、上記の長さがなくても通行できることがあります。そのため、ぎりぎりかもしれない、足りないかもしれない、という場合には、都道府県又は市町村の道路課(道路管理者)に問い合わせるのがよいでしょう。
「道路幅員証明書」は各自治体から発行してもらえます。自治体によっては、これに通行車両最大幅を記載してくれているところもあり、申請後の審査が迅速に終わることが期待できます。
車両制限令に抵触していても、使用できるとされる場合には、道路管理者から特殊車両通行認定(承認)を受ける必要があるので、少しやることが増えることを覚えておきましょう。この認定がおりれば、前面道路の幅に対して大きすぎる車両であっても通行できることになり、運輸局から運送業を営む許可を得ることができます。
ただ、この通行認定は、2年間の許可期間がありますので、期限が切れる前に更新手続が必要なことを忘れないようにしてください。この
前面道路が国道の場合
国道の場合は、幅員証明書は不要です。
前面道路が私道の場合
車庫の前の道路が私道の場合は、持ち主、つまり当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認が必要です。
「通行承諾書」という書面を作成することが通常です。
私道の場合、公道と違って幅員の確認は不要です。ただし、通行権限があることを「通行承諾書」で証明できなくてはなりません。
また、公道と私道が接する地点については、幅員制限がありますので、車両制限令に従う必要があります。
前面道路が認定外道路の場合
車庫の前の道路が里道などの認定外道路の場合、国道などと違って道路管理者から幅員証明書をもらうことができません。
この場合は、この道路の該当する位置図(公図)などを提出することが求められます。
認定外道路は通行権限の証明も、幅員の確認も不要です。
ただし、私道の場合と同様で、公道と私道が接する地点については、幅員制限がありますので、車両制限令に従う必要があります。
まとめ
今回は、運送業の方が必ず必要となる車庫について解説しました。
事業用の車には厳しい制限が設けられているため、物件を見つけることも大変な場合があります。幅員制限は、自治体によって車庫接道の道路幅員と通行可能車両の大きさの運用が違います。
いくつもの確認を道路管理者、運輸局とすることはかなりの労力と時間がかかります。効率よく運送業を営むための確認及び申請などは、専門家である行政書士までお気軽にお問合せください。