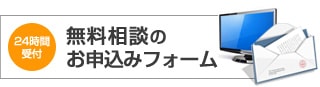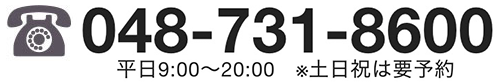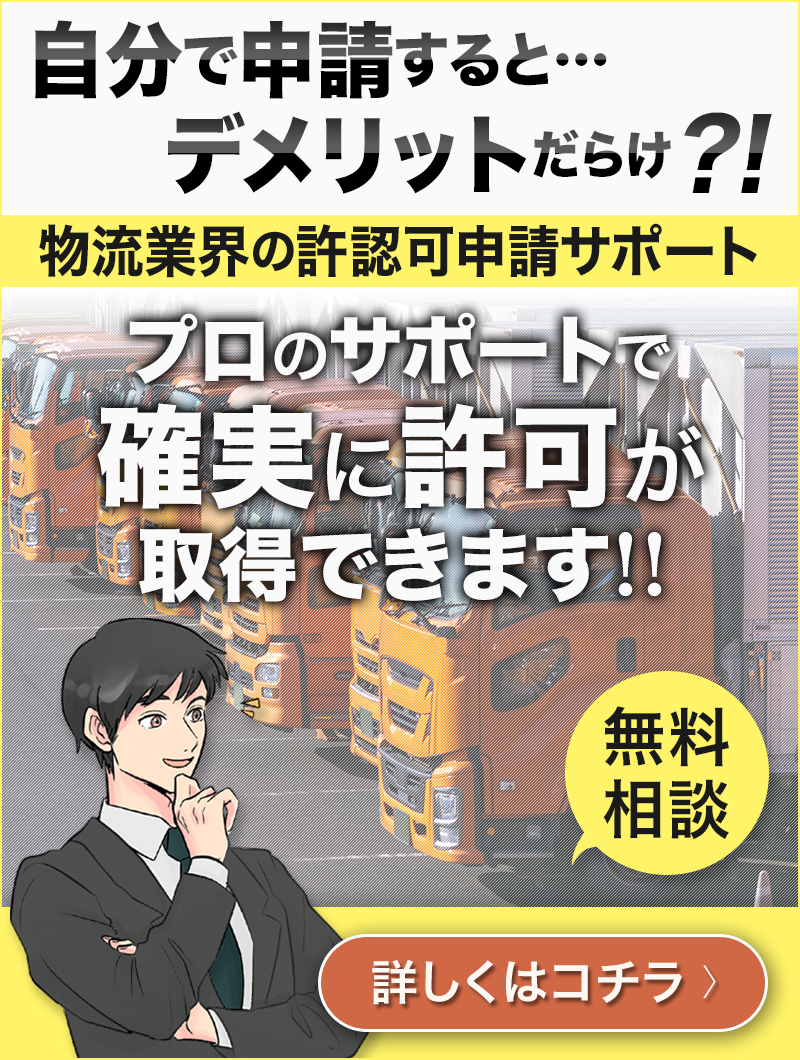運送業の駐車場(車庫)の変更(新設・移転・廃止)を解説

一般貨物自動車運送事業者が、駐車場を変更したり(移転)、新たに作り(新設)、それに伴い今の駐車場を使わなくする(廃止)場合には、書類をたくさん用意することが求められます。
申請が認められないと、当然駐車場として使用することができないので、変更申請は事前に行うことが原則です。それをしないと、一時期停める場所がなくなってしまいます。
そのようなことにならないため、こちらでは運送業の駐車場(車庫)の変更(新設・移転・廃止)を詳しく解説いたします。
最初にすること
移転先の駐車場、新しく作る駐車場が、運送事業用の車庫としての要件を満たしているか、確認することが大切です。
簡単に説明すると、
1.営業所からの距離制限を満たすか
|
・東京23区、横浜市、川崎・・・20キロメートル以内 ・その他の関東及び山梨県・・・10キロメートル以内 |
2.車両と車両の間の距離と、車両と駐車場の壁や境界との距離は、最低50センチメートルの間隔がとれるか
3.車庫の前の道路が
|
・相互通行の場合、2トンクラスで5メートル以上、4トン・大型車クラスで5.5~6メートル以上 ・一方通行の場合、 2トンクラスで2.5メートル以上、4トン・大型車クラスで3m以上であるか |
私道の場合、持ち主から使ってもいいという許諾が得られるか
4,他人から借りる場合に2年以上もしくは自動更新の契約になっているか
5.他社の車庫との区画が明確に分かれているか(線やロープなどを用いる)
6.法令(農地法、都市計画法)違反でないか
を確認してください。
詳しくは、車庫の条件の記事を参照してください。
必要書類
①一般貨物自動車運送事業の「事業計画変更認可申請書」に必要事項を記載して提出します。営業所や、車両の数などの変更も同時に行えます。
社名や役員の変更は、届出書なので、別の書類が必要です。
②案内図、見取図、平面図(求積図)
車両台数と、それに対する十分なスペースがあるか、出入り口の前面道路の幅員が法令にのっとっているか、ということを記載します。
面積計算をして記載しましょう。
③賃貸借契約書、使用承諾書
車庫の使用権原を証明するために必要です。
自分の所有地であれば、不動産登記簿謄本を添付すればいいです。
駐車場の敷地が他人から借りる場合には、賃貸借契約書が必要です。車庫の場所の住所、契約期間、借りる敷地の面積、使用目的が明記されていることは必ず確認しましょう。
車庫の変更は、初めて車庫の許可を得る時と同様の条件が必要です。
|
・使用目的が「駐車場」「車庫」であること
・契約書と申請書の住所が合致していること
・2年以上の契約、または2年未満であるが“自動更新”であることが明記されていること |
賃貸借契約書に不備がある場合に、使用承諾書が必要となります。賃貸借契約書は内容の訂正ができない、もしくは難しい場合が多いのです。だから、使用承諾書は記載のないものについて追加して補足する役割をします。
④幅員証明書
駐車場の出入り口の前の道路は、一定以上の幅がなければ違法となります。
一方通行か双方通行かどうか、車両の大きさ(2トン、4トン、大型車)で変わります。
国道の場合は不要です。
⑤車庫の写真
⑥事業用自動車の運行管理等の体制
営業所に車庫が併設されていない場合に必要です。
提出先
管轄の運輸支局に提出します。
審査期間について
審査が終わるまでにおよそ2,3か月かかります。書類に不備があれば、さらに時間がかかるため、慎重に準備しましょう。
認可がおりたら、新しい車庫を使用することができるようになります。同時に、前に使っていた車庫は運送事業の車庫としては使用できなくなります。
まとめ
今回は、運送業の方が必ず使う車庫の変更等について解説しました。
事業用の車には厳しい制限が設けられているため、変更について認可申請をしていない場合、申請・届出義務違反となり法令に基づいて罰則の対象となります。
また、変更には2,3か月と長い期間が必要となるため、急ぎで事業計画を変更するという時もすぐには反映されないため、注意してください。リスク回避及び運輸局に行き面倒な手続を迅速に進めるためにも、専門家である行政書士までお気軽にお問合せください。